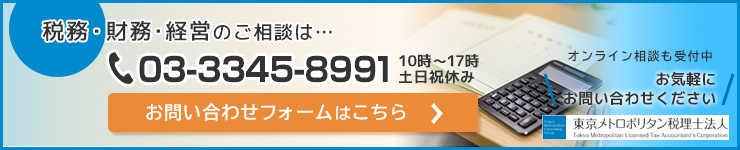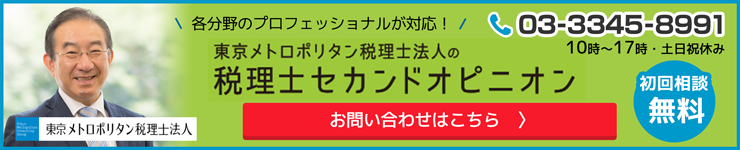実践!事業承継・自社株対策
死亡退職金の受取人【実践!事業承継・自社株対策】第244号

2025.04.10
Q:私は40年以上前、20代で会社を創業し、現在まで経営をしております。
後継者については長男が会社に入っており、少しずつ株は贈与していますが、最終的には相続で承継すれば良いかと思っています。
いずれは社長を譲るものの、できるだけ現役で事業に関わっていきたいと思います。相続税対策としては、役員退職金がそれなりになると思うので、それで相続税を支払うのは十分可能かと思っていますが、何か注意すべき点はありますでしょうか?
A:将来的な株式評価や相続税がどれくらいになるのか、また、その際の退職金がいくらになるのか、ある程度の年数を想定して、シミュレーションしてみることが重要かと思います。
ただ、役員退職金が高過ぎる場合は、税務上否認されることもありますので、退職金規定も見直しておくことも必要です。
その際、確認して欲しいのが、退職金の受取人です。
生存退職金はもちろん、本人が受け取ることになりますが、問題は死亡退職金です。
亡くなるまで役員をやっていた場合は、死亡退職を原因として、遺族が退職金を受け取ることになります。
退職金規定に、死亡退職の場合の受取人がどのように書かれているかを確認して欲しいと思います。
受取人の第一順位が配偶者とされていたり、単に相続人としか書いていないこともあります。
株式の承継による相続税を、退職金で賄おうとするのであれば、その退職金が後継者にいくようになっていなければなりません。
退職金の受取人が配偶者である場合に、株式を相続した長男がその退職金を相続税に使おうとすると、母親から贈与を受けるか、借りるかなどしなくてはなりません。
そうなると贈与税の支払いや、借入金の返済などを行っていくことになり、非常に厄介な問題が起こってきます。
そうならないためには、退職金規定にたとえば次のような付記をしておくことが考えられます。
「ただし、遺言により受取人の指定があった場合はその遺言に従うものとする。」
このように付記しておいた上で、遺言書を作成し、死亡退職金の受取人に長男を指名しておけば、問題なく退職金を相続税の納税に使うことができます。
是非、現在の退職金規定を見直してみてください。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
上記は生命保険金などもそうですね。生命保険金を相続税の納税に充てようと思えば、相続税を払う人が受取人になっていないと上記と同じような問題が起こります。
配偶者が保険の受取人であることが多いのですが、配偶者は相続税がかからないことが多いですね。もちろん、配偶者の生活資金も重要ですが、納税資金という面でも保険を見直しておくことも大事かと思います。
メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001685356.html