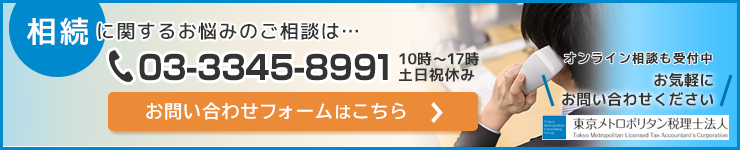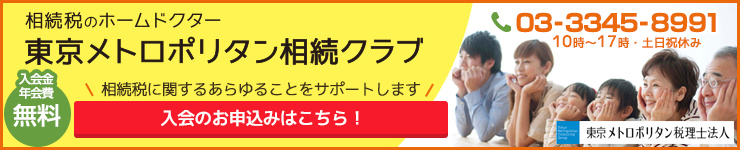実践!相続税対策
建築中の建物敷地の小規模宅地等の特例【実践!相続税対策】第675号

2024.12.25
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
今回は、11月20日に配信した建築中の建物におけるお話の第2弾となります。
前回は、建築工事中の建物の相続税評価額の算定方法についてお話させていただきました。
本日はそういった建物がある際に、土地の評価額を減額することのできる小規模宅地等の特例の適用可否について、お伝えしていきます。
結論からいうと、建築工事中の建物がある土地であっても、要件を満たせば小規模宅地等の特例を使うことができます。
小規模宅地等の特例には、いくつかの種類がありますが、被相続人の居住用として使用していた宅地等について確認してみましょう。(特定居住用宅地等として330m2まで評価額が80%減額される小規模宅地等の特例)
まず、小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等が居住用として使用していた宅地等」に該当するかどうか、判定を行う必要があります。
これは、被相続人が相続開始の直前において、その宅地等の上にある建物に生活の拠点を置いていたかどうか、により行います。
相続が開始した際に、建築工事中だった場合は、その宅地等の上に建物がまだ建っていないことから、生活することができません。
そうなると、小規模宅地等の特例も適用できないように思います。
ただし、被相続人の居住用宅地等であるかどうかの判定を、相続開始直前の一時点のみで行うのは、実情に即したものとはいえない、とも考えられます。
そこで、建築工事中の居住用建物の敷地については、次の(1)と(2)の要件を満たす場合には、小規模宅地特例の適用を認めることにしています。
(1) 建築工事中の建物が、被相続人または被相続人の親族の所有するものであり、かつ、被相続人の居住用として使用されると認められるものであること。
(2) 原則として、相続税の申告期限までに、その建物またはその敷地を取得した親族等が、その建物を居住用として使用していること。
上記親族等とは具体的には、次のAもしくはBに該当する者となります。
A その建物またはその敷地を取得した被相続人の親族
B 相続人と生計をーにしてした親族
上記取り扱いは、建築中の建物の敷地すべてについて、小規模宅地等の特例の適用ができないと、却って課税の公平性が保てなくなるからです。
したがって、一定の要件を満たせば、建築中の建物についても、小規模宅地等の特例の適用が認められることとなっております。
なお、被相続人が相続開始直前において、この建築中の建物とは別の建物に居住していた場合で、その宅地に小規模宅地等の特例を適用した場合は、適用することができません。
以上、建築中の建物については、減額措置が適用できないと思われがちですが、きちんと要件を満たすことで大幅に相続税評価額を減額することが可能となります。
高齢で建築中に亡くなった場合のことが心配なときなどは、是非、専門家に相談することをお勧めします。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
相続メルマガについては、本日が2024年最後の配信となります。
また、年が明けてからの配信は1月8日からとなっておりますので、ぜひ翌年もお読みいただければと思います。
本年も大変お世話になりました。
皆さま、どうぞよいお年をお迎えくださいませ。
私は、こたつの中でお蕎麦をすすりつつ、のんびり新年を迎えようと思います…
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html