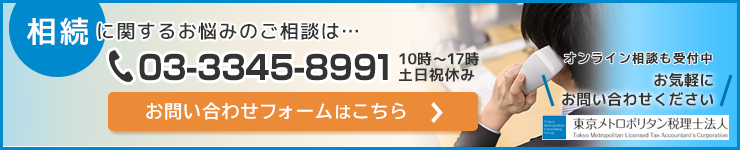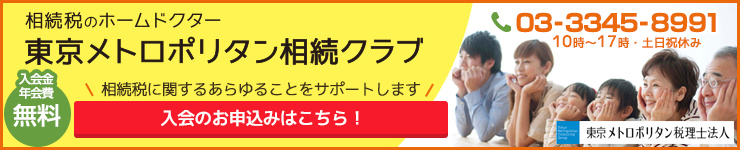実践!相続税対策
今年の申告、暦年課税か相続時精算課税か【実践!相続税対策】第681号

2025.02.12
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2月に入っていますので、確定申告の準備をされている方も多いかと思います。
所得税の確定申告は、今年は2月17日月曜日からですが、贈与税の申告は、2月1日(今年は2月3日月曜日)から既に始まっています。
今年は令和6年の贈与税の大幅改正後、初めての申告になりますね。
今まで110万円以下の贈与をした場合は、暦年課税の基礎控除以下なので、申告をしなくて済みました。
令和6年以降も、110万円以下は贈与税はかかりませんが、これは、暦年課税を適用しているのか、相続時精算課税を適用しているのか、どっちなの?ということになります。対象になる方の場合ですが。
令和6年改正では、相続時精算課税にも110万円の基礎控除が設けられたからです。
同じ110万円の基礎控除といっても、どちらを適用しているのか、ということです。
何もしなければ、暦年課税を適用していることになります。
相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与をする場合に、選択することができます。
この年齢は、贈与する年の1月1日の年齢ですから、これには注意しておかなければいけないですね。
この対象になる方の場合には、どちらを選択するか、です。
相続時精算課税制度を選択すれば、110万円を超えたとしても、累計で2,500万円まで贈与税はかからない、ということになります。
ただし、その贈与を受けた財産は、贈与をした人の相続時に、相続財産に加算されて相続税で税金を精算することになります。
令和6年に改正された相続時精算課税の基礎控除110万円は、この2,500万円の枠とは別に、非課税になる、ということです。
したがって、相続時精算課税で110万円を贈与した場合は、贈与時にも、相続時にも税金がかからない、という使い方によっては、とても有利になる制度です。
対して暦年課税の方の110万円の基礎控除は、贈与時には税金はかかりませんが、その後7年内に贈与した人が亡くなった場合には、相続財産に加算されてしまう、という改正も令和6年にありました。
暦年課税が厳しくなって、相続時精算課税には特典ができた、ということです。
したがって、今後の贈与はどちらを使うかということも、対象になる方は考えた方が良いのかと思います。
昨年、親から贈与を受けた方などは、申告前の今からどちらの制度を使うか、選ぶことができます。
110万円以内であれば、どちらを選んでも非課税ではありますが、その後の扱いが上記のように変わってきます。
なお、相続時精算課税を使う場合は、それを使う最初の年に、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、110万円以内の贈与であれば、申告をする必要はありません。上記届出書だけを出せばOKです。
出し忘れた場合は、暦年課税になってしまいます。
なお、一度、相続時精算課税を選択した場合は、その贈与者との間では、暦年課税に戻ることはできません。
その他の方からの贈与については、届出を出さない限りは暦年課税となります。
昨年贈与を受けた方は、改正後初めての申告ですので、上記のようなことを是非、考えてみてください。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
いよいよ確定申告モードになってきました。ウチの事務所にも資料がどんどん来ています。とにかくこの1か月の間にかなり業務が集中しますので、計画的に効率よくやっていかないと大変なことになります。
以前にも書きましたが、簡単な申告は是非、国税庁のHPから電子申告でやってしまうことをお奨めします。毎年毎年改良されてきて、とても使いやすくなってますよね。
是非、覗いてみてはいかがでしょうか?
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html