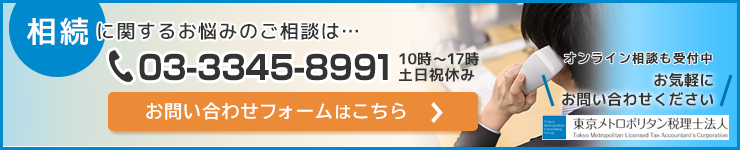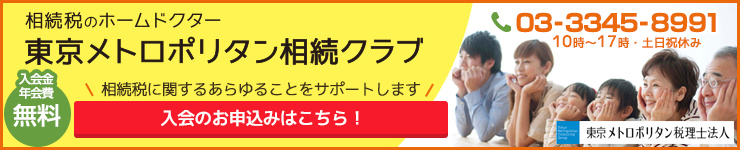実践!相続税対策
相続税の申告要否判定コーナーの活用【実践!相続税対策】第687号

2025.03.26
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続税は、被相続人の財産や債務がどのくらいあるのか、相続人が何人いるかによって、申告要否が決まります。
ご家族やご自身に相続が発生した場合に、申告が必要なのかどうか、今まで気にされたことがない方は、まずは、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で確認してみてはいかがでしょうか。
所得税の確定申告をご自身で作成されている方は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成しているかと思います。
同じような入力形式で、配偶者の有無、子の人数などを入力することで、申告要否の判定基準となる基礎控除額が計算されます。
引き続き、土地、建物、有価証券、現金・預貯金、生命保険金、その他の財産、相続時精算課税適用財産などを入力することで、相続財産の合計額が算出されます。
借入金があればその残高、過去に贈与を受けたことがある場合はその贈与金額など、概算金額を入力するだけで、申告要否判定結果がわかります。
ある程度入力したところでデータ保存もできますので、財産の増減によって、保存データを利用して判定を再開することも可能です。
こちらも確定申告書等作成コーナーと同じ要領ですね。
さらに、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例などの適用可否についても要件など記載されており、特例適用の税額計算シミュレーションをすることもできます。
ただし、この税額計算シミュレーションは、あくまで税額の目安を示すものですので、シミュレーション結果を相続税の申告書に転記することはできません。
実際の相続税申告にあたっては、様々な判断が必要になってきますので、専門の税理士に依頼することをお勧めいたします。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」は、項目ごとに簡単な説明もあります。
複雑な評価方法などには対応していませんので、概算額で参考程度にご利用ください。
一般的な家族構成や相続財産であれば、こちらの計算ソフトで十分かと思います。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html