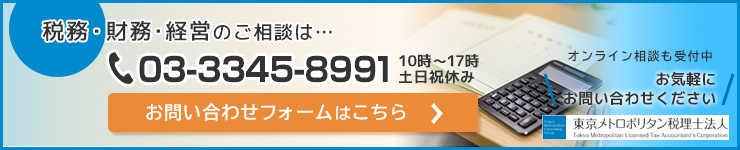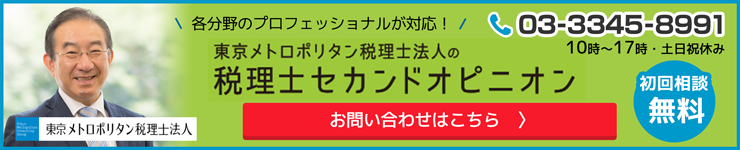実践!事業承継・自社株対策
除外合意と固定合意【実践!事業承継・自社株対策】第236号

2025.02.13
Q:先週の質問の回答で、経営承継円滑化法による民法特例に、除外合意、固定合意というものがある、とのことでしたが、これらはどのようなものなのでしょうか?
A:先週のご質問にあったように、財産の多くが自社株である場合に、後継者が自社株をほとんどすべて承継すると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。
そうなると遺留分の侵害額について、金銭での支払いを求められたり、自社株を分散して承継せざるを得なくなり、事業活動の継続に好ましくない状況になりかねません。
そこで、これらを防いで円滑な事業承継を実現するために、経営承継円滑化法では「遺留分に関する民法の特例」が設けられています。
この民法特例に、除外合意や固定合意があります。
除外合意とは、後継者と現経営者の推定相続人の全員が、自社株を遺留分の対象となる基礎財産から除外することで合意することです。
これにより、後継者は承継した自社株について、遺留分を請求されることがなくなりますので、安心して事業を承継することができます。
固定合意とは、遺留分の対象となる基礎財産に算入する自社株の価額を、後継者と現経営者の推定相続人全員が合意した時点の時価に固定することです。
これにより、合意後に後継者の努力により自社株の価額が上がっても、その部分には遺留分の主張を受けることがなくなります。
この合意時の時価については、税理士、公認会計士、弁護士等による証明が必要となります。
除外合意や固定合意を受けるためには、一定の要件を満たした上で、以下のような手続きを行う必要があります。
1.後継者と推定相続人全員で合意し合意書を作成する
2.経済産業大臣の確認を受ける
3.家庭裁判所の許可を受ける
また、一定の要件とは次の要件を満たすことが必要です。
1.会社の要件
・中小企業者であること
・合意時点で3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
2.現経営者の要件
・過去または合意時点において会社の代表者であること
3.後継者の要件
・合意時点において会社の代表者であること
・現経営者から贈与等により自社株を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること
以上の手続きを経ることで、会社の承継をスムーズに行うことができるようになりますので、財産のほとんどが自社株であるような場合は、検討してみると良いのではないでしょうか。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
今日の民法特例、除外合意ができれば後継者にとっては非常に安心ですが、実際なかなか私どもの事務所でもそこまでの事例はないですね。自社株が多いとしても他に何らかの財産があったり、他の相続人が会社の後継について理解を示してくれていたりすることが多いので、そこまで行かないのかと思います。
ただ、もめそうな時にはこういう制度もある、ということを頭に入れておくといいのかな、と思いますね。
メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001685356.html