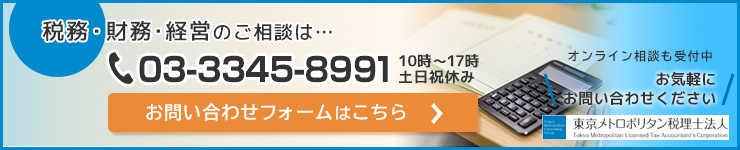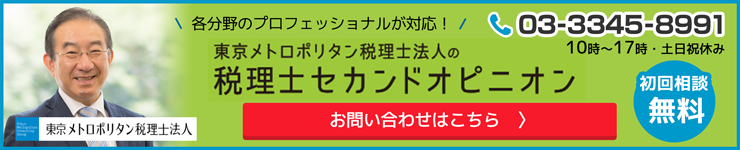実践!事業承継・自社株対策
持株会社を設立する意味【実践!事業承継・自社株対策】第246号

2025.04.24
Q:最近、2つの銀行からそれぞれ持株会社を設立することを勧められました。
以前にも勧められましたが、よくわからなかったので何もしませんでした。
ただ、知り合いの社長は持株会社を作っている人が多いようです。
結局、持株会社を設立する意味は何なのでしょうか。
A:多くの意味合いとしては、事業承継の円滑化や、株価引き下げ効果を期待して、持株会社を設立する方が多い認識です。
事業会社(建築業であったり、飲食業であったり、実際に事業をしている会社)の株式を保有するだけの持株会社を設立して、事業承継を進めることがあります。
つまり、後継者が持株会社を設立し、先代社長保有の事業会社の株式を買い取ることにより、事業承継を実施する方法です。
持株会社が事業会社の株式を購入する際、課税問題を発生させないためには、購入価格は法人税法上の価格と呼ばれている非常に高い価格で購入する必要があります。(類似業種比準価額50%+純資産価額50%など)
先代社長としては、後継者の事業会社が株式を高く買ってくれることにより、引退後の生活が充実・安定したリ、相続の際の納税資金や、遺産分割がやりやすくなるため、場合によっては非常に効果を発揮することもあります。
ただし、先代社長としては株式を売却するわけですから、その売却益に譲渡所得税20.315%がかかってきます。
上記のとおり株価は非常に高くなりますので、相当の税金になる可能性があります。
一方、持株会社の方は、購入のための借入金が多額になる可能性があります。
この借入金の返済は、通常は事業会社からの配当金を原資とすることになりますが、事業会社の経営状況によっては、負担がかなり大きくなる可能性があります。
なお、100%保有会社からの配当金は、全額益金不算入(税金がかからない)になることも銀行がアピールする点です。
銀行としては、持株会社が株式を買い取る時の資金を提供(貸出)できる可能性があることが、提案してくる大きな理由ではないでしょうか。
会社に寄り添った銀行でしたら、良い提案をしてくださるところもありますが、銀行の利益のために持株会社を設立してもあまり意味がないときもあります。
銀行もビジネスとして提案していることを考えれば、こちらの方も持株会社の意味合いをきちんと把握して、必要性をしっかり考える必要があります。
株価引き下げ効果については、持株会社が類似業種比準価額を採用できれば、事業会社の利益や純資産に影響を受けずに、株価を引き下げることができます。
ただ、持株会社には落とし穴があり、株式保有特定会社に該当する場合は、類似業種比準価額を採用することができません。この場合は、基本、純資産価額で評価することになります。
株式保有特定会社とは、総資産の50%以上が株式等である会社であり、まさに持株会社はこれに該当する可能性が高くなります。
このため、株式以外に事業会社の不動産を保有したり、不動産賃貸業等を行わないと、なかなか類似業種比準価額を採用することは難しいでしょう。
その他にも、持株会社には株価引き下げ効果があります。
それは、純資産価額を計算する際に、相続税評価額と簿価との差額について法人税等相当額(37%)を、減額することができるということです。
このため、たとえ類似業種比準価額を採用できなくても、保有する事業会社の株価が上がった場合は、その値上り益の37%は、評価を圧縮できるということになります。
しかし、上述のとおり、持株会社が事業会社の株式を購入する際は、法人税法上の非常に高い価格で購入します。
つまり簿価が高くなります。
結果として、相続税評価額が簿価より高くなるのはいつになるのかと思うほど、高くなることがあります。
このような場合は、株価引き下げ効果はないといえます。
持株会社の設立は、すべての効果を把握しようとすると、相当複雑になり、判断が難しい場面が多々あります。
一度設立したものを途中でやめることは、ほぼ不可能と言えますので、是非、慎重にご検討いただければと思います。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
ついに春という暖かさになってきましたね。むしろ夏に近いのかもしれません。
ゴールデンウィークも今のところ東京は、比較的良い天気になりそうですね。お出かけされる方は、お気を付けていってらっしゃいませ。
メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001685356.html